知ってるようで知らない?「減塩」と「塩分控えめ」の意外な違い!
こんにちは!最近スーパーに行くと、やたらと「減塩」とか「塩分控えめ」って書かれた商品を見かけませんか? 健康志向が高まる中で、気になって手に取ってみるけど、「あれ?この2つって何が違うの?」って思ったこと、ありませんか?
実はこれ、ただの言葉遊びじゃないんです。ちゃんとした「ルール」があるって知っていましたか?今回は、意外と知らないこの2つの違いについて、トレンド雑記ブログ風に、分かりやすく、そしてちょっと掘り下げてお話していきますね!
そもそも、なぜ「減塩」「塩分控えめ」が人気なの?
まずはこの話題から。最近、健康診断で「血圧が高いですね」と言われたり、テレビで「高血圧は怖い」なんて特集を見たりする機会が増えましたよね。日本人は昔から醤油やお味噌といった塩分を多く含む調味料をよく使う食文化なので、ついつい塩分を摂りすぎちゃいがち。
そんな中で、おいしさはそのままに、健康にも気を使える「減塩」や「塩分控えめ」の商品は、まさに現代の私たちのニーズにぴったり!食卓の選択肢が広がる、嬉しいトレンドなんです。
気になる本題!「減塩」と「塩分控えめ」の決定的な違い
さあ、いよいよ本題です!結論から言うと、この2つの言葉は、日本の法律やガイドラインで厳密に定義が決められているんです。
1. 「減塩」は、比較対象がある!
「減塩」と表示するためには、「同じメーカーの、同じ種類の通常の商品」と比べて、塩分を25%以上カットしていること、というルールがあります。
たとえば、A社から「普通の醤油」と「減塩醤油」が出ていたとします。この「減塩醤油」は、A社の「普通の醤油」と比べて塩分が25%以上少ない、という証拠。つまり、明確な比較対象があって、その差がはっきりと分かる場合に使える表示なんです。
「この減塩タイプは、いつものあの商品よりもしっかり塩分が少ないんだな」と、私たちがパッと見て理解できるようになっているんですね。
2. 「塩分控えめ」は、明確な基準がない!?
一方、「塩分控えめ」はどうでしょうか?実は、この表示には「減塩」のような厳しいルールや、具体的な数字の基準はありません。
「控えめ」というのは、あくまでもその商品の特徴を示す、いわばイメージ的な表現なんです。なので、メーカーによって基準がバラバラだったり、もともと塩分が少ない商品に表示されていたりすることもあります。
例えば、B社が新しく出したおせんべいに「塩分控えめ」と書いてあるけど、比較対象となる「普通の」おせんべいがB社から出ていない…なんてこともあり得ます。
賢く選ぶためのポイント!
この違いを知ると、スーパーでの商品選びがちょっと変わってきますよね。
- 「減塩」 は、いつもの商品をヘルシーなものにチェンジしたい時にぴったり!例えば、いつもの醤油を減塩醤油に、いつものお味噌を減塩味噌に変えるだけで、無理なく塩分を減らすことができます。
- 「塩分控えめ」 は、新しい商品を試すときに注目!「この商品は全体的に塩分が少なめなんだな」と理解して、他の食品とのバランスを考えながら取り入れるのがおすすめです。
まとめ:知っているとちょっと得する豆知識
「減塩」と「塩分控えめ」。この2つの言葉は、一見同じように見えて、実は意味が全く違いました。
- 「減塩」 → 比較対象がある!塩分25%以上カット!
- 「塩分控えめ」 → 比較対象がない!イメージ的な表現!
これからは、商品の裏の成分表示を見たり、メーカーのウェブサイトをチェックしてみたりすると、もっと賢く、楽しく商品選びができるはず。おいしく、そして健康的な食生活を送るための小さな一歩として、ぜひ参考にしてみてくださいね!
それでは、また次回の記事でお会いしましょう!

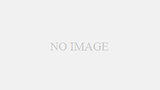
コメント